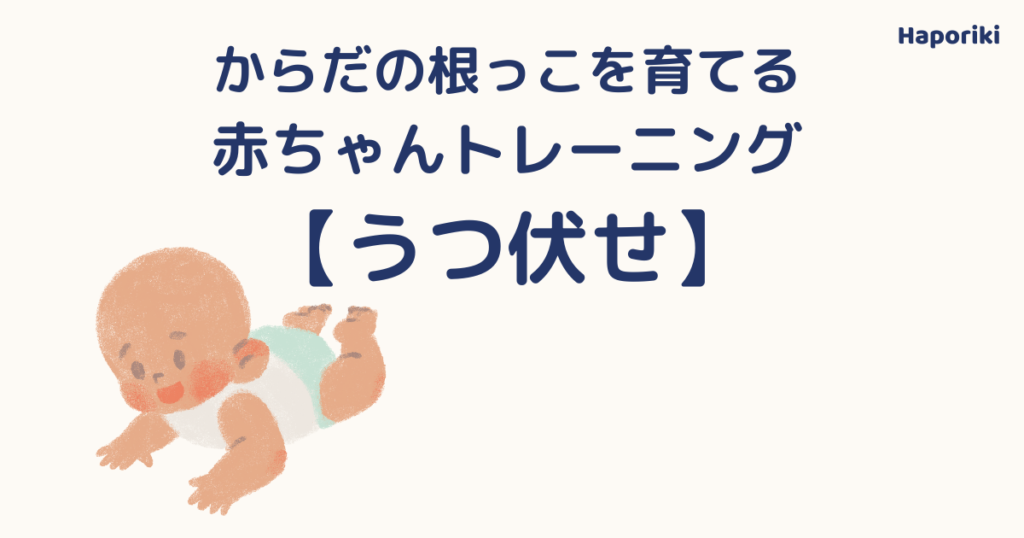
ご覧いただきありがとうございます!
【からだの根っこを育てる赤ちゃんトレーニングシリーズ】第二弾です!
前回までの記事をご覧いただいてからこの記事を読んでいただくと、より理解が深まると思いますのでよろしければこちらもご覧ください。
ざっくり概要だけお伝えすると…
子どもの運動能力を伸ばすためには、からだの根っこ=コアを育てることが大切で、
コアを育てるには赤ちゃんの発育発達に沿った動きを再学習することが大切。
泣くことで赤ちゃんは体幹機能を高めている。
そうすることで、身体を安定させることができるようになる。
ということをお伝えしてきました。
詳しくは上記の記事をご覧ください。
今回は、赤ちゃんの動き【うつ伏せ】についてお伝えしていきます。

目次
うつ伏せの発達
赤ちゃんの発育発達過程の一つ、【うつ伏せ】がなぜトレーニングになるのか?
それを紐解くには、まずはうつ伏せの姿勢がどのようにして発達していくのかをお伝えする必要があります。
ということでここからは、うつ伏せの発達についてお伝えします。
はじめてのうつ伏せ
生まれた赤ちゃんは、仰向けで大きな声で泣いて体幹の安定性を高めることができると、(詳しくはこちらをご覧ください。)
仰向けの状態で頭を左右に動かしたり、手足をバタバタと動かせるようになっていきます。
そうした動きが見られるのは、体幹の安定性が高まってきている証拠でもあります。
その段階に入ってきたら次は、うつ伏せの姿勢を経験していきます。
はじめてのうつ伏せは、赤ちゃんが自力でうつ伏せになることはできないので、
大人が手助けをしてうつ伏せにしてあげます。
うつ伏せをしたばかりのころは、ほんの一瞬なら頭を床から持ち上げることができます。
でもまだ首も据わっていないので、頭を持ち上げられるのは一瞬で、顔の向きを左右にコントロールすることもできません。
また、腕は床にべったりと着いたままで、足もまっすぐに伸びきらないです。

(↑イメージ画像)
オンエルボー姿勢
うつ伏せをたくさん経験するようになっていくと、次第に首が据わるようになっていき、
頭をより長い時間持ち上げていられるようになります。
また、顔の向きを左右にコントロールできるようになり、正面に向けた状態でキープすることもできるようになります。
(からだの根っこを育てるという話とは少し逸れた話にはなりますが、
首が据わって顔の向きをコントロールできるようになると、目の前にあるものをじっと見つめたり、
動くものを目で追いかけたりといった、視線をコントロールすることができるようになっていきます。
そうして目の機能も向上していく時期でもあります。)
また次第に自分の腕で自分の身体を支えることができるようになります。
肘をついて身体を支えて頭を持ち上げたうつ伏せの姿勢を、オンエルボー姿勢(下画像)と言います。


オンエルボー姿勢が取れるようになってくると、足もまっすぐ伸ばせるようになっていきます。
オンハンズ姿勢
オンエルボー姿勢より高い位置に頭を持ち上げることもできるようになっていきます。
これまでは肘をついて身体を支えていましたが、手のひらをついて身体を持ち上げることができるようにもなっていきます。
手のひらをついて身体を持ち上げた状態をオンハンズ姿勢(下画像)と言います。


オンハンズ姿勢から、片手を床から離して目の前にある物に手を伸ばすこともできるようにもなります。
飛行機姿勢(ピポットプローン)
うつ伏せ姿勢の発達は最終的に、
頭を上げたまま両手を床から離し、両足を伸ばして、飛行機のような姿勢をキープできるようになります。
このような姿勢をピポットプローン(下画像)と言います。

このように赤ちゃんはうつ伏せ姿勢を発達させていきます。
頭を持ち上げる→オンエルボー姿勢→オンハンズ姿勢→ピポットプローン
これらの動きを通して、赤ちゃんはからだの根っこを育んでいくのです。
ではなぜこれらの動きをすることがからだの根っこを育むことに繋がるのか?
うつぶせによってどんな運動機能を獲得していくのか?
ここからはそれらについてお伝えしていきます。
うつ伏せによって獲得できる運動機能
うつ伏せ姿勢を取ることで、赤ちゃんはどんな運動機能を獲得していくのでしょうか?
大きく分けて以下の3つの機能を獲得することができます。
- 身体を伸展させる力の向上
- 下部体幹の安定性の向上
- 肩甲帯の安定性の向上
それでは、それぞれについて詳しく説明していきます。
身体を伸展させる力の向上
赤ちゃんはうつ伏せを経験するまでは、身体を丸めた姿勢(屈曲姿勢)が優位になります。
うつ伏せでの運動経験を通して、身体を伸展させる力(身体を反らせる方向の力)を発達させていきます。
前述のはじめてのうつ伏せのときには、主に頸椎(首の骨)の伸展の力を身につけます。
オンエルボー姿勢・オンハンズ姿勢のときには、主に胸椎(胸あたりの背骨)の伸展・腰椎(腰あたりの背骨)伸展の力を身につけます。
ピポットプローンの姿勢のときには、主に背中全体の伸展の力と、股関節(足の付け根あたり)を伸展させる力を身につけます。
このようにうつ伏せを経験することによって、赤ちゃんは初めて重力に抗して身体を持ち上げるための伸展筋群を発達させていきます。
仮にうつ伏せを経験せずに発達していくと、
伸展させる力を持っていないので、四つ這いのときには股関節を伸展させることができず、足を蹴り出せず前に進めない、ということになってしまいます。
下部体幹の安定性の向上
下部体幹というのは、その名の通り、体幹の下の方のことを指します。
おおまかにいうと、おへそ~骨盤のあたりまでの部分のことです。
そして下部体幹の安定性が高まるということは、腰が据わるというイメージが近いかと思います。
ではなぜうつ伏せ姿勢によって下部体幹の安定性が高まるのか?
はじめてのうつ伏せ→オンエルボー姿勢→オンハンズ姿勢の順に、重心の位置が徐々に頭側からおしり側に移動していきます。
実際に同じ姿勢をとってみてください。
すると、自分の体重がかかる位置がおしりの方に下がっていくのがわかると思います。
下部体幹に体重がかかるようになるということは、自分の体重を下部体幹で支える必要が出てくるということです。
体重を支えるためには、下部体幹の安定性が必要になります。
そうして下部体幹の安定性を向上させていくのです。
肩甲帯の安定性の向上
肩甲帯というのは、おおまかにいうと、肩甲骨や上腕などを含む「肩周り」のことです。
肩甲帯が安定するということは、肩甲骨などの骨が適切な位置に安定した状態のことです。
赤ちゃんのころは関節が緩いため、簡単に肩が抜けてしまうなんていう話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
肩甲帯が安定すると、そんな簡単に肩が抜けるなんてことはなくなります。
ではなぜうつ伏せ姿勢で肩甲帯の安定性が高まるのか?
オンエルボー姿勢、オンハンズ姿勢をとると、肩にも体重がかかります。
実際に同じ姿勢をとってみるとわかりやすいと思います。
赤ちゃんはこの姿勢をとるときに初めて肩に体重がかかる経験をします。
肩で体重を支えるために、肩甲帯の安定性を高める必要があるのです。
こうして肩甲帯の安定性を向上させることによって、将来的に力強い投球ができるようになるなどの効果があります。
肩甲帯の安定性が増すと、片手を離すこともできるようになり、ほしい物に片手を伸ばすようになります。
そうすると、左右への重心移動が起き、その重心移動はずり這いの動作に繋がっていきます。
このように、うつ伏せ姿勢を取ることによって、身体を伸展させる力を発達させ、重力に抗して身体を支える機能を発達させていくのです。
からだの根っこを育てること=「重力」のある環境下で生きていくための身体機能を発達させること
(詳しくはこちらを参照ください。)
と考えると、うつ伏せ姿勢はまさしくからだの根っこを育てる赤ちゃんトレーニングと言えますね。
【うつ伏せ】を再学習する方法
ここまで、うつ伏せの姿勢を経験することで様々な運動機能を獲得していくことをお伝えしてきました。
赤ちゃんの発育発達過程の動きを子どもも大人も取り入れることで、その動きによって獲得できる運動機能を「再学習」できます。
つまり、子どもも大人も【うつ伏せ】によって獲得できる運動機能を再学習して獲得することができるのです。
では具体的にどう取り入れるか、いくつか例をご提案します。
うつ伏せでボクシング
一人がオンエルボー姿勢またはオンハンズ姿勢でうつ伏せになります。
もう一人がうつ伏せになった人に対面して座ります。
座った人が、うつ伏せになった人の前に手のひらを出します。
うつ伏せになった人はその手のひらにタッチします。
これをテンポよく繰り返します。
手が届かないようで届きそうな場所(上下左右ランダム)に手を出してあげたり、
素早く手を出して引っ込めて、相手の素早い反応を引き出したりなど、
お子さんと一緒にゲーム感覚で楽しく遊んでみてください!
このようにボクシングをするように手にタッチをする遊びをすることで、
自ずと背中を反らせて、身体を持ち上げて、伸展させる筋群を発達させることができます。
飛行機体操
これはピポットプローンの姿勢を飛行機体操と呼んでいます。
両手両足を床から浮かせて、できるだけ頭を床から高く上げた姿勢をキープします。
その間、大きな声で1から10まで数えます。
大きな声で数を数えることで、コア機能を高めることもでき一石二鳥です。
ただ10秒飛行機体操をするだけでは退屈だと思うので、
お子さんと対戦形式で、どっちが長くピポットプローン姿勢をキープできるか勝負!のようにゲーム性をもたせて遊ぶのもいいかもしれません。
まとめ
今回は、からだの根っこを育てる赤ちゃんトレーニング第二弾として、【うつ伏せ】についてお伝えしてきました。
うつ伏せの姿勢の発達について、うつ伏せによって獲得できる運動機能について、ご理解いただけましたでしょうか?
赤ちゃんはうつ伏せ姿勢をとることで、身体を伸展させる力を発達させ、重力に抗して身体を支える機能を発達させていきます。
それと同時に下部体幹の安定性や肩甲帯の安定性の向上にも一躍買ってくれています。
また今回は詳しくはお伝えしていませんが、うつ伏せ姿勢は目の機能にもとっても重要な役割を果たしてくれています。
赤ちゃんは2か月くらいからどんどん積極的にうつ伏せにさせてあげてください。
まだしっかりと頭を上げられない子をうつ伏せのままにして長時間目を離してしまうと、
窒息してしまう恐れもあるので、大人がそばで見守れるときにうつ伏せにしてあげてくださいね。
そして大きくなったお子さんも、楽しみながらうつ伏せの姿勢をとる機会を増やしていきましょう。
そうすることで子どもたちのからだの根っこを育てていきましょう!
では、今回はここまで!
次回は、からだの根っこを育てる赤ちゃんトレーニング第三弾【寝返り】についてお伝えする予定です。
お楽しみに!